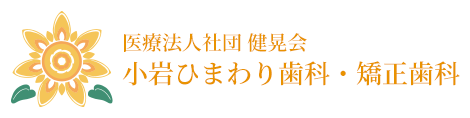日本歯科医学会に参加してきました棋士の羽生さんの決断力を磨く、というテーマのセミナーは経営や診断においても活かせる大変有意義な講演でした。
ここが要点というのを直感で導き、多数の選択肢から2個くらいに絞って、熟考しています。
羽生さんは何手先まで読もうとしていますか?とよく聞かれるそうです。
相手のいる勝負において、3手先まで読むだけでも6万通り考えなくてはなりません。
しかし、それは人間の脳では不可能で、大局観を身につける事が重要です。 経験を積んでくると暗記→大局観へと思考の幅が広がってきます。
長考に好手なし、と言われるように、心理的な不安に立ち向かう時間、答えに迷ってる時に行動を起こすのは危険だと考えられます。
この話を聞いて、自分の診療や経営にも、同じ事が言えると感じました。
短時間で決断力できる時は、自信を持って行動ができてパフォーマンスを100%発揮できると考えているので、普段から、こういう場面に陥ったらどう解決するか考えておく、調べておく事が大切だと思います。
結果が良くない時に2パターンあると考えられます。
単なる不調の時は、気分を変える事が効果的です。自分は最善の手を打っているのに、結果が出ない時は、最善の手を変えずに、気分を変える為に美容院に行ったり、美味しい物を食べる。
どういう時に、良いパフォーマンスを発揮できるかというと、リラックスして楽しんで仕事できてる時だと様々な研究でも証明されています。
プレッシャーを感じてる状態は、いいところまできてるものです。
限界突破できる寸前で、少し頑張れば成長できるイメージを持たせる事が重要です。
ミスを起こした時に、心理的動揺が起きて、判断を謝る事があります。
ミスをした後に、目の前の状況から挽回する為の最善手に集中する事が大切です。(悩んだ際はレントゲン撮る等して気分を変える事が大切だと感じました)
ミスした後に、反省と検証をしてクヨクヨと考えてるとミスを連発してしまうリスクがあるからです。
1番悪い状態は、ミスによってヤル気を失った状態なのです。
一方、悪手を打っていて調子悪い時には、原因を考えて改善する事が必要で、周囲の人間が、ダメだよと諭してあげる必要があります。
YouTubeで早送りして見た将棋の試合は15分で忘れてしまうが、じっくり考えながら見た試合は、ずっと記憶に残ると言われています。
ブロック化して記憶する事が有用と言われています。
AIとチェスの対戦では、1996年にAIが買っています。
相手の立場にたって考えましょう、と良く言われてるように、相手の状況や心理状態を評価して、それを予測して、3手目を読む力が必要とされてます。
αゼロは15万局の将棋対局を深層学習して、AI同士で3000万局対戦させて、自ら学ぶようにして強くなったAIなので、セカンドオピニオン的に使う棋士が多いそうです。
人間の思考の、盲点を見つけたり、確認するのに利用できるので、他の分野にも同様に利用されると考えられます。自動運転に対して、夕方や朝方の光と影が交差する時間帯は、人間が得意で、夜道のように安定した時間帯は、AIが得意だそうです。AIの評価の外側にある、人智を超えた画期的な発見が人間には可能ですし、推論と学習を同時にできます。